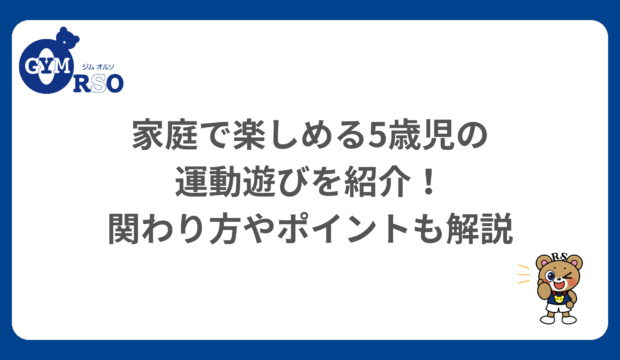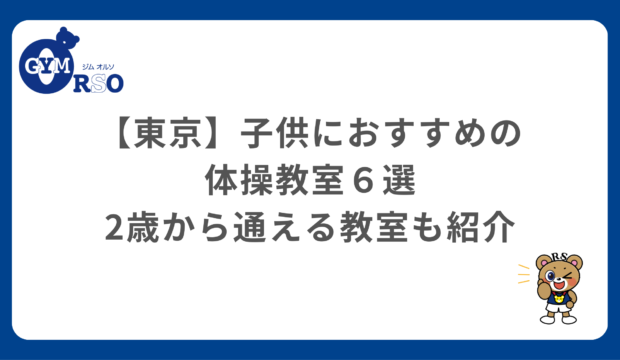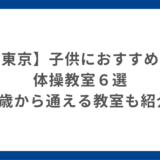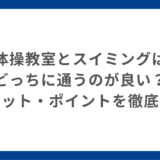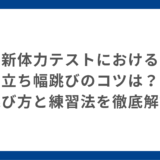平均台を使った遊びは、子どもの身体バランスや集中力、危険回避力など、さまざまな能力を高めるうえで有効です。ただし、正しい練習方法を知らないと転倒や恐怖が生じやすく、思うように成果を得られない場合もあります。
本記事では、平均台を渡る際のコツと鍛えられる力、注意すべきポイントについて詳しく解説します。
平均台で養える能力
平均台を使った遊びは、楽しみながら身体機能を高められる点が魅力です。ここでは、子どもが平均台で養える能力について紹介します。
バランス感覚
子どもが平均台で遊ぶと、バランス感覚や平衡感覚が養われ、日常生活でも転倒しにくい体づくりにつながります。足裏から伝わる情報を脳が処理する過程で、姿勢を安定させる力が高まるためです。
さらに、重心の移動に伴い体幹も刺激されるため、結果として身体全体の調整力が向上します。たとえば、「姿勢保持の安定・左右差の少ない動き・運動への自信向上」などのメリットが期待できます。
日常動作をスムーズに行えるようになれば、外遊びやスポーツにも積極的に取り組む意欲が育つでしょう。また、片足立ちや方向転換に慣れることで、足首や膝の柔軟性が高まり、体にかかる負担を分散しやすくなる点も見逃せません。
身体能力
平均台で遊ぶと、下半身だけでなく上半身を含む全身の筋力が自然と鍛えられます。足先から体幹、腕に至るまで連動して動く場面が増えるため、基礎体力の底上げが可能です。
踏み込む瞬間に太ももの筋力が養われ、バランスをとる際には腹筋や背筋が刺激されます。総合的な運動は、日々の活動に必要な持久力や瞬発力にも好影響を及ぼし、子どもが遊びの延長で運動能力を伸ばせる点が魅力といえるでしょう。
さらに、平均台の狭い足場での動作は、足首や膝の関節を柔軟に保つきっかけにもなります。結果として、ジャンプや走行など多彩な動きを身につける土台となり、スポーツへの興味を高める大きな要因にもなります。
自信・自己肯定感
平均台での成功体験は、子どもの自信や自己肯定感を育むうえで重要です。小さな達成でも「自分にできる」と実感すると挑戦意欲が高まり、次のステップへ挑む意欲を高められます。
また、大人の声かけやサポートがあると達成感が増し、恐怖心を軽減しながら自信を深められる好循環が生まれるのも特徴です。
「あと少しで渡れるよ」と励ますと、子どもは前向きな気持ちを維持できるでしょう。積み重ねた成功体験は「もっとやりたい」との意欲を育み、学習や運動など幅広い場面で積極的な姿勢を発揮するきっかけになります。
失敗を糧に前進する心の強さを養えるため、自己肯定感は高まり、子どもにとって将来にわたる大きな財産となるでしょう。
集中力・注意力
平均台を渡るときは足元を踏み外さないように進む必要があるため、集中力と注意力が自然に磨かれます。視線や重心、足の置き場など、多くの情報を同時に把握しながら動くことで、脳と身体の連携がスムーズになる点がメリットです。
また、少しの揺れや傾きにも敏感になるため、危険を早期に察知する力が養われるでしょう。
集中力が身につくと、学習面でも落ち着いて問題に取り組めるなど、思わぬ形で相乗効果を発揮します。さらに、大人が「ゆっくりで大丈夫」と声をかけながら見守ると、余裕をもって周囲を確認する習慣を育めるのも大きなメリットです。
結果として、判断や注意配分の的確さが日常生活全般に活かされます。
危険回避能力
平均台は高低差や落下のリスクがあるため、子どもが自ら安全を意識するきっかけをつくります。どのように足を運べば転倒を防げるかを考える過程で、危険を回避する判断力が自然と育まれるのが大きな特徴です。
たとえば、一歩先の足場を確かめてから踏み出す習慣がつくと、万が一バランスを崩しかけても素早く体勢を立て直せるようになります。
また、目線を遠くに向けて周囲の状況を把握する力が高まれば、人混みや自転車など予測不能な動きにも早めに対応できるでしょう。危険回避能力は、道路の横断や遊具の使用など、あらゆる日常シーンで役立つ重要なスキルとなります。

平均台をうまく渡るコツ
平均台を上手に渡るためには、子どもの段階に合わせて難易度を少しずつ引き上げていく工夫が欠かせません。
視線の置き方や腕の使い方など基本動作を理解したうえで、恐怖心をやわらげながら確実に成功体験を積ませることが大切です。
ここでは、平均台をうまく渡るコツについて詳しく解説します。
遠くを見る
平均台を渡るときに足元ばかり見ていると、体が前かがみになりバランスが乱れやすくなります。そこで、少し先の目標地点や遠くを見据えることで頭が起き、視線と背骨が一直線に近い状態を保てるのがメリットです。
実際、スポーツ選手も走るときや跳ぶときに視線を前方に向けることで、スムーズな動作を行っています。平均台でも原理は同じで、体の重心を安定させやすくなるうえ、一歩先を予測して足を出しやすくなるのがポイントです。
周囲の安全確認もしやすくなるため、慣れないうちは「足元ではなく、進む先を見よう」と具体的に声かけをすると、子どもも意識しやすくなります。
両手を横に広げてバランスをとる
両手を横に大きく広げる姿勢は、バランスをとるうえで最もシンプルで効果的な方法です。
腕を飛行機の翼や鳥の羽になぞらえると、子どもにもわかりやすくイメージさせられます。両腕を左右に伸ばすことで重心が左右対称に近づき、片側に傾いた際にも素早く姿勢を修正しやすい点がメリットです。
また、肩の力を抜くと肘や手首まで連動し、微妙な揺れを自然に補正できます。子どもがふらついたときは「翼でバランスをとるイメージだよ」と伝えると、遊びながら体で覚えられるでしょう。無理に腕を上げすぎず、水平に構えるのが安定感を保つコツです。
段階的に高くする
ビニールテープで床に線を引いて歩く練習から始めると、子どもは地面との段差を気にせずに平衡感覚を体験できます。1歳児など、まだ平均台が怖い子にはこのアプローチが有効です。
その次のステップとして、牛乳パックを利用してごく低い平均台をつくり、少し高さのある環境に慣れさせます。
慣れてきたらパックを積み重ねて徐々に高さを変え、さらに距離を長くするなど段階を踏んで難易度を調整しましょう。恐怖心を最小限に抑えながら「できた!」との達成感を積み重ねることで、バランス力だけでなく自信の育成にもつながります。
難易度を徐々に上げる
平均台に初めて立つときは、手をつないで安定感をもたせるところからスタートします。慣れてきたら横歩きに移行し、さらに足をすりながら移動する擦り歩き、後ろ向きで歩く、最後には小さなジャンプなど、段階的にレベルアップしていくのが効果的です。
変化を少しずつ加えると、子どもが失敗への恐怖を抑えながら挑戦でき、成功体験を重ねられます。大人は「今日は横向きで歩けたね」「次は後ろ歩きに挑戦しよう」などと声をかけ、子どもが意欲を持ち続けられる環境をつくりましょう。
最終的には、走るような動作や複雑なステップにも応用できるだけのバランス能力を身につけられます。

平均台を渡るときの注意点
平均台遊びは楽しいですが、転倒などのリスクも含まれています。そのため、安全に配慮した準備が必要です。
子どもの予測不能な動きにも素早く対応できるよう、マットの敷き方から周囲の見守り体制まで、複数の面で注意を払う必要があります。特に、複数の子どもが同時に使う場合は、互いにぶつかったり押し合ったりしないためのルールづくりも大切です。
以下では、具体的な安全管理のポイントを紹介します。リスクを最小限に抑えつつ、子どもが安心して楽しめる環境を整えましょう。
平均台の周りにマットを引く
万が一の転倒に備えて、平均台の周辺には適切なマットを敷きましょう。マットが厚めでクッション性があると、子どもが落下したときの衝撃をやわらげる効果が期待できます。
さらに、隙間があると足を挟むなどのトラブルが発生しやすいため、複数のマットを並べる場合は継ぎ目をしっかり合わせて設置するのがポイントです。
落ちやすい箇所(平均台の端・高さが変わる部分など)を重点的にカバーすると、子どもにも「ここは危なくない」との安心感を与えられます。大人はすぐ手を差し伸べられる位置にスタンバイし、危険を未然に防ぎましょう。
子どもから目を離さない
平均台では、子どもが予想外の動きをする可能性が高いため、常に視界に入れておくことが基本です。特に、慣れたころに急にふざけたりスピードを上げたりする子もいるため、油断は禁物といえます。
マットを敷いていても、落下の仕方によっては大きな衝撃を受けることがあるため、こまめに声かけをしながら動きを確認しましょう。複数の子どもが同時に遊ぶ場合は、保護者や指導者も複数人で見守る体制をとると安全性が高まります。
万が一トラブルが起きたときに素早く対処できるよう、連携を意識しておくことが大切です。
前後の子どもとしっかり距離をとる
平均台上では、子ども同士が近すぎると転倒時に巻き込まれるリスクが高まります。そのため、一人ひとりのスペースを十分に確保し、順番を守って歩くよう指導しましょう。
先に渡っている子が停止や後退をした際、後ろの子が十分な反応時間を取れるようにするためにも、距離を空けることが重要です。スムーズに進む子と慎重に進む子の速度差がある場合は、互いにぶつからないよう間隔を調整します。
また、複数の平均台を並行して配置する場合でも、隣との間隔を適切に取り、安全に配慮した動線を確保しておきましょう。
平均台に関するよくある質問
Q1. 平均台を渡ることで子どもはどんな力が身につきますか?
A. バランス感覚、体幹を含む全身の筋力、集中力、注意力、危険回避能力、そして自己肯定感などが養われます。遊び感覚で取り組むことで、日常生活やスポーツにも活かせる力が自然と身につきます。
Q2. 平均台をうまく渡れるようになるには、どんな練習が効果的ですか?
A. 「視線は遠くを見る」「両手を横に広げてバランスを取る」などの基本を押さえることが大切です。はじめは床に線を引いて歩く練習から始め、徐々に高さや難易度を上げていくと、恐怖心を抑えながら確実に上達できます。
Q3. 安全に平均台遊びをするために、どんなことに注意すればよいですか?
A. 平均台の周囲にマットを敷く、子どもから目を離さない、前後の距離をしっかり取るなどが重要です。特に複数人で遊ぶときは、ぶつかったり押し合ったりしないようなルールづくりと見守り体制が必要です。
まとめ
平均台は、バランス感覚や身体能力、そして自信・注意力など多方面の成長を促す遊具です。段階的な練習と安全管理を徹底すれば、子どもは恐怖を抑えながら着実に上達できます。
遠くを見る、両手を広げるといった基本のポイントを押さえ、マットの利用や子ども同士の距離にも配慮しつつ、楽しみながら成長を支えていきましょう。
また、ジムオルソでは2才から通うことができるコースがあるため、小さい頃から平均台の練習ができます。お子様の年齢やレベル、やる気に合わせた、少人数制でアットホームな雰囲気のクラスを用意しています。
たとえば、2歳〜3歳が対象の「プレキッズ」をはじめ、小学3年生〜大人が対象の「バク転教室」までさまざまなクラスがあります。体操教室への入会を検討されている方は、ぜひジムオルソの無料体験にお越しください。
ジムオルソの店舗一覧・無料体験予約はこちら
平均台を渡るために参考になる動画はこちら
ジムオルソ公式YouTubeチャンネルはこちら