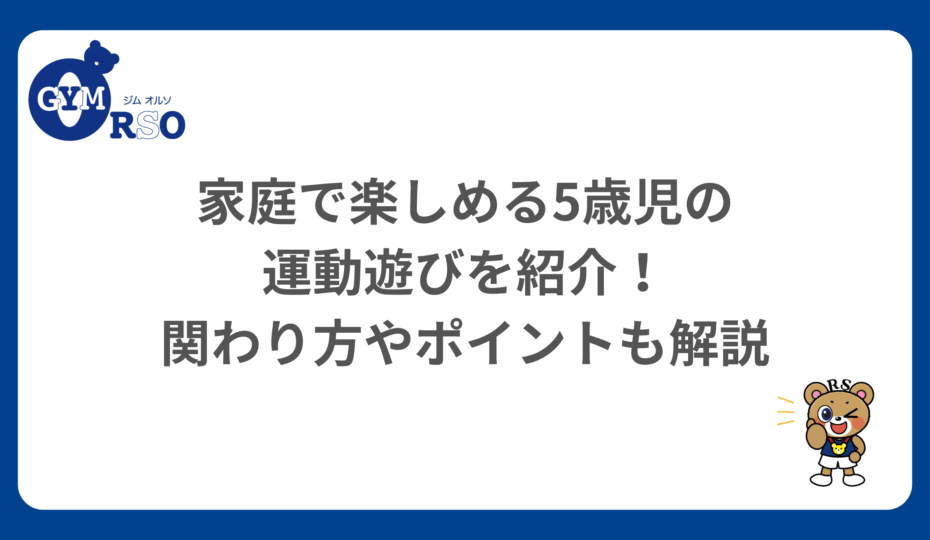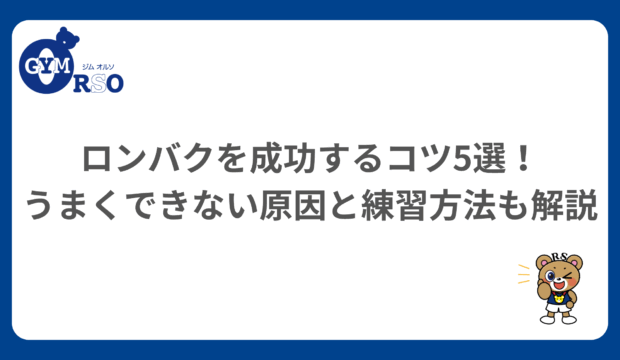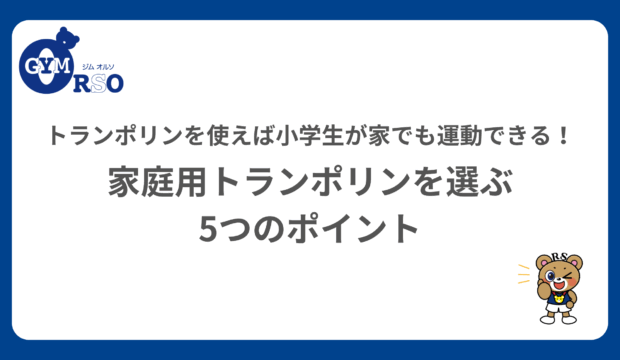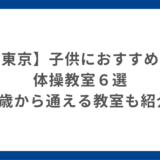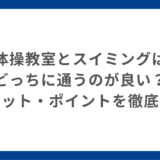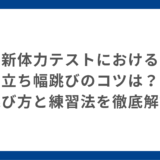本記事では、5歳児にみられる運動発達の目安、運動遊びのねらいとポイントを解説します。また、家庭でできるおすすめの運動遊び5選も紹介します。
4歳児におすすめの運動遊びをこちらの記事で紹介していますので、あわせてチェックしてみてください。
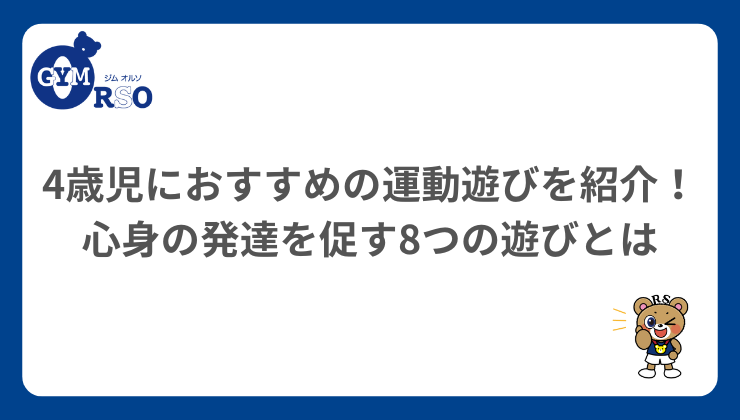
2025.07.03
4歳児におすすめの運動遊びを紹介!心身の発達を促す8つの遊びとは
4歳児は3歳児と比べて、平均身長も100cmを超え、身体がしっかりとしてきます。この時期に身体の動かし方を覚えたり、運動能力を高めたりすることは重要です。 また、身体の成長の他に、心の成長も目覚ましく、運動遊びを通じて友だちとの関わり方を覚えたり、協調性、社会性などを身につけたりできるとよいで...
5歳児の運動発達の目安
5歳児は、運動能力が大幅に向上する時期です。複雑な運動や、道具を用いて工夫した遊びを楽しめるようになってきます。以下は、5歳児にみられる運動発達の目安です。
- 自分でなわを回してなわとびをする
- 数分間の曲の振り付けを覚えて踊る
- 鉄棒で前回りをする
- 片足跳びやスキップをする
- ぶらんこに立ってこぐ
- キャッチボールをする
あわせて、次のような社会性の発達もみられます。
- 複雑なルールを理解する
- 友だちと協力する
- 自分の感情を少しずつコントロールできるようになる
- 相手の気持ちを想像する
また、時計や時間に興味を持ち、日常生活でも時間を意識するようになるのもこの時期の特徴です。
こうした成長をサポートするためにも、運動遊びを取り入れていきましょう。
5歳児の運動遊びのねらい
運動遊びとは、体を使って行う遊びのことです。幼児が1人で楽しめるものから、複数人で協力して遊ぶものまでさまざまな種類があります。
ここでは、5歳児が運動遊びをすることにどのような意味があるのか解説します。

身体能力を高める
運動遊びには、子どもの身体能力を高める効果があります。近年では、子どもが体を動かす機会が減少しており、運動能力や発達への影響が懸念されています。
運動遊びを積極的に取り入れることで、以下のようなさまざまな身体能力の向上を図る効果が期待できるのです。
- 筋力
- バランス感覚
- 柔軟性
- 瞬発力
- 持久力
- 反射神経
- 空間認識力、身体認識力
工夫して目的を達成する喜びを経験する
5歳児は、複雑な運動や、複数の動きを組み合わせた運動、複雑なルールの理解などができるようになる時期です。運動遊びを通して、目的を達成するために自分なりに考えて行動し、うまくできなかったときには工夫したり、他の方法を試したりする力が育まれます。
運動遊びを通して工夫したり、達成の喜びを感じたりする体験は、自己肯定感や主体性を育てることにもつながります。
社会性を育む
運動遊びでは、ルールを守って遊ぶことや、他の人と協力する場面が多くあります。自分の意見を伝えたり、妥協して譲り合ったりしながら、遊びのなかで自然に社会性が育まれていくのです。
また、子ども同士で遊ぶときには、年下の子に教えてあげる、困っている子に声をかけてあげるといった思いやりを育てる機会も生まれます。
このように、運動遊びを通して社会性を育むための重要な体験ができます。
5歳児の運動遊びに大切な3つのポイント
運動遊びでは、子どもが楽しめることが重要ですが、それに加えて意識したい3つのポイントを紹介します。さまざまな動きを取り入れる
運動遊びでは、さまざまな動きを取り入れることが大切です。身体能力は「走る」「跳ぶ」「投げる」「取る」「止まる」など、多様な動きを経験することで養われます。
これらの動きを運動遊びのなかで自然に経験することで、楽しみながら身体能力を高められるでしょう。
また、さまざまな動きを経験していると、新しい運動に柔軟に対応しやすくなります。
運動遊びを通して、子どもができるだけ多くの動きを経験できるよう工夫しましょう。
社会性を養う運動遊びを取り入れる
5歳児の運動遊びでは、社会性を育めるような遊びや関わり方を意識することも大切です。たとえば、少し複雑なルールを設けたり、子ども同士で協力して遊ぶ機会を作ったりするとよいでしょう。
また、5歳児は時間にも興味を持ちはじめる時期です。時間を意識して行動できるような声かけをするのもよいでしょう。
「〇時になったら片づけようね」といった時間を意識した声かけを通して、行動の見通しを持てるようサポートします。
「ジムオルソで」は、挨拶や礼儀を学び、集団行動を通して社会性を育むことも大切にしています。
お子さまの運動能力だけでなく、社会性も育みたい方は、ぜひ「ジムオルソ」の無料体験にご参加ください。
安全な環境を整える
運動遊びをする際には、けがを防ぐために安全な環境づくりが欠かせません。5歳児は活発に動き回るため、広めの場所を確保し、周囲に危険なものや不要なものを置かないようにしましょう。
床が滑りやすくないか、転倒しやすいものがないかも確認しておくと安心です。

5歳児が家庭でできるおすすめの運動遊び5選
ここでは、5歳児が家庭で楽しめるおすすめの運動遊びを5つ紹介します。だるまさんが転んだ
「だるまさんが転んだ」は、特別な準備が不要で室内でもできる運動遊びです。鬼役の人が、後ろを向いて「だるまさんが転んだ」と言い、振り返ります。
その間に、他の人は鬼役の人に近づきます。鬼が振り返ったとき、他の人がその場で動きを止め、動いてしまった人は負けです。
「だるまさんが転んだ」の、走ったり止まったりする動きによって、体幹の筋肉、バランス能力、瞬発力などが鍛えられます。
また、判断力や、ルールを理解し守るといった社会性も育まれます。
マット遊び
マット遊びは、マットや布団の上で、さまざまな動きを取り入れられる遊びです。たとえば、前転や後転、逆立ち(大人が足や腰をサポート)などの運動を楽しめます。
また、子ども同士で遊ぶときは、マットや布団の上に向かい合って立ち、手で相手を押し合う遊びもあります。相手を押し出した人が勝ちです。
マット遊びでは、体の柔軟性を向上させ、日常生活では体験できない姿勢や動きを学べます。
けがを防ぐため、マットや布団は大きめのサイズを用い、周囲に危険なものがない場所で行いましょう。
なわとび
初めてなわとびに挑戦する場合は、次の練習をすると習得しやすいでしょう。まず両足でジャンプする練習をして、次に片手でなわを持って回す練習をします。
慣れてきたら、両手でなわを後ろから前に回して、そのなわを跳び越えましょう。
跳べるようになったら、決めた時間内に何回跳べるか挑戦したり、跳んだ回数を表に記録したりすると達成感を味わえるとともに、楽しみながら続けられます。
また、複数人で遊ぶ際は、長なわとびに挑戦してもよいでしょう。
大人がなわを回し、子どもが全員で一緒に跳んだり、順番になわをくぐり抜けたりする遊びが楽しめます。
なわとびは、全身の筋力を鍛え、バランス感覚、リズム感覚、手足を同時に動かす力、集中力などを育みます。
裾が長いスカートやズボンは、ひっかかりやすく危険なため、避けるようにしましょう。
ボール遊び
ボールを使うと、年齢に応じたさまざまな遊びが楽しめます。5歳児になると、キャッチボール、ボール蹴り、ボーリングなどを楽しめます。
キャッチボールは、両手で持てる大きさのボールを用いるとよいでしょう。
大人と子どもが向かい合って立ち、1人がボールを投げて相手が受け取ります。
転がしたボールを受け取ることから始め、次にバウンドするよう投げて受け取ります。
徐々にバウンドさせないように進めましょう。
ボール蹴りでも、両手で持てる大きさのボールを使います。
大人と子どもが向かい合って立ち、ボールを蹴り合ったり、的に向かって蹴ったりします。
はじめは、子どもの前にボールを置いて蹴る練習をするとよいでしょう。蹴るときに勢いをつけすぎて転倒しないよう、慣れるまでは大人が横でサポートする、椅子に座って蹴るなど、安全に配慮して行います。
ボーリングは、空のペットボトルを並べ、ボールを転がして倒す遊びです。ペットボトルやボールのサイズを変えたり、ペットボトルに少量の水を入れたりすると、変化をつけることもできます。
ボール遊びでは、距離感や方向感覚、集中力、瞬発力などを育めます。
おにごっこ
おにごっこは、鬼役の人が、他の人を追いかける遊びです。また、缶蹴り、氷鬼、色鬼、高鬼、手つなぎ鬼など、さまざまなバリエーションも楽しめます。
おにごっこでは、瞬発力や持久力、観察力などを養えます。
小学生の体力づくりに役立つ運動メニューをこちらの記事で紹介していますので、お子様の成長にあわせて参考にしてみてください。
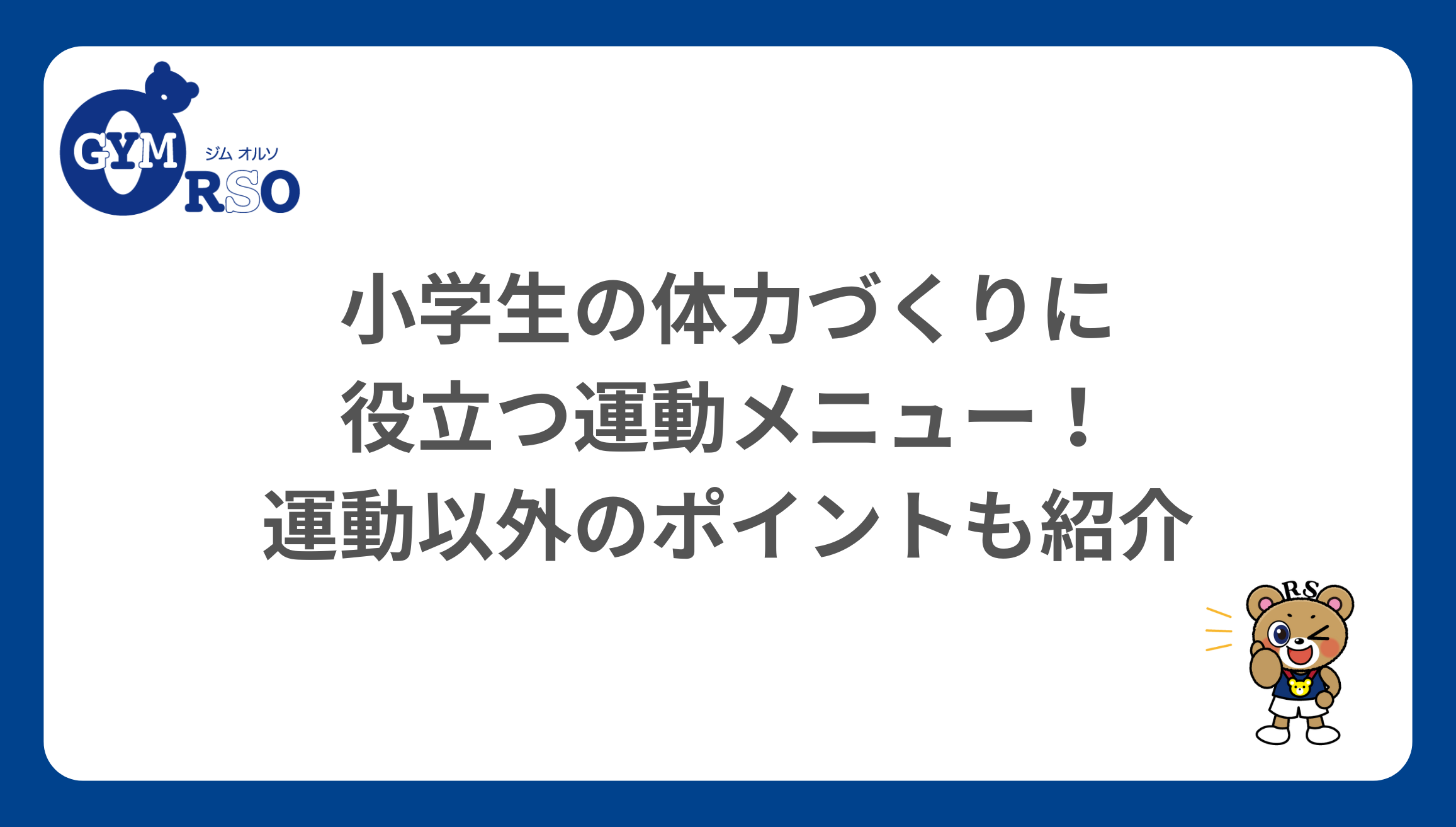
2025.08.28
小学生の体力づくりに役立つ運動メニュー!運動以外のポイントも紹介
小学生の子どもが「疲れやすい」「集中力がない」と感じる原因には、体力がないことが挙げられます。 小学生の体力は年々低下しており、体力が低下すると免疫力が落ちたり怪我をしやすかったりと良くない影響が数多くあります。 本記事では、手軽に始められる小学生の体力づくりに適した運動メニューや、...
5歳児の運動遊びに関するよくある質問
Q1.5歳児の運動遊びにはどんな効果がありますか?
A. 体力・バランス・柔軟性などの身体能力を高めるだけでなく、ルールを守る力や友だちと協力する力などの社会性も育まれます。自己肯定感や工夫する力も身につきます。Q2.家庭で5歳児が楽しめる運動遊びには何がありますか?
A. 「だるまさんが転んだ」「マット遊び」「なわとび」「ボール遊び」「おにごっこ」などがおすすめです。室内・屋外を問わず楽しめる遊びで、体を動かす習慣をつけられます。Q3.5歳児の運動遊びで気をつけるポイントは?
A. さまざまな動きを取り入れること、協力し合えるルールを設けること、安全なスペースを確保することが大切です。転倒しやすい物を片付け、危険がない環境で遊ぶようにしましょう。まとめ
5歳児は、運動能力が大幅に向上するとともに、社会性も発達し、ルールを守り友だちと協力して遊ぶようになってくる時期です。体を使って行う運動遊びは、このような成長をサポートするのに効果的です。
5歳児の運動遊びは、身体能力を高めるだけでなく、社会性を育む効果も期待できます。
運動遊びにおいて大切な3つのポイントは「さまざまな動きを取り入れる」「社会性を養う運動遊びを取り入れる」「安全な環境を整える」ことです。
ジムオルソでは、お子様の年齢やレベル、やる気に合わせた、少人数制でアットホームな雰囲気のクラスを用意しています。
たとえば、2歳〜3歳が対象の「プレキッズ」をはじめ、小学3年生〜大人が対象の「バク転教室」までさまざまなクラスがあります。
体操教室への入会を検討されている方は、ぜひジムオルソの無料体験にお越しください。