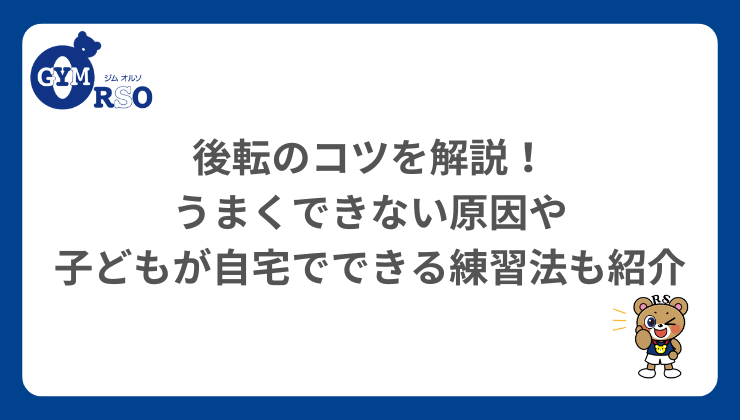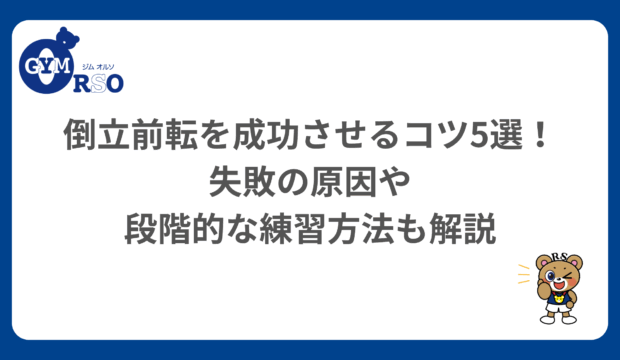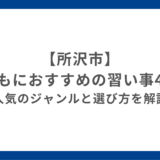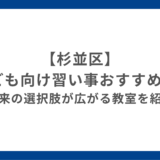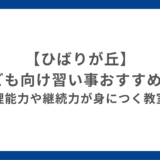本記事では、子どもが後転を苦手と感じやすい理由、うまくできない原因、そしてできるようになるための3つのコツを解説します。
子どもが後転を苦手と感じやすい理由
子どもが後転を苦手と感じやすい理由は、主に次の2つです。- 日常生活にない動きが必要とされる
- 見えない方向に向かって回転する恐怖心

子どもが後転をうまくできない原因
子どもが、後転をうまくできない主な原因には、勢いが弱い、体が伸びている、手の平を床につけられていないことなどがあります。ここでは、それぞれ解説します。勢いが弱い
後転をうまくできない原因の1つに、後ろに倒れる勢いが弱いことが挙げられます。ある程度の勢いがなければ、うまく回れません。しかし、後方に倒れることに対して怖さを感じ、ゆっくりと倒れてしまうケースがあります。また、倒れた際に、肘が床につくと、回転の勢いを抑えてしまうこともあります。このような場合は「ゆりかご運動」や「エビの姿勢」を実践することが、怖さを和らげるのに有効です。
体が伸びている
後転をうまくできない原因として、後方へ倒れる際に、体が伸びてしまうことがあります。体が伸びていると、回転の勢いを阻害してしまうため、うまく回れません。構えたときから最後まで、おへそをしっかりと見るよう意識しましょう。手の平を床につけていない
手の平をしっかりと床につけられていないことも、うまくできない原因の1つです。後転を成功させるためには、後方に倒れた後、手の平で床をしっかりと押す必要があります。手の平をしっかりと床につけていなければ、床を押せず、勢いが弱まってしまうため、着地までしっかりと回れないのです。肘が外に向いて開いていたり、肘が床についていたりすると、手の平を正しくつけられません。手の平をつけることが難しい場合は、肘の向きや位置を確認してみましょう。
子どもが後転をできるようになるための3つのコツ
ここでは、後転が上達するための、3つのコツを紹介します。耳の横に手を添えて体を丸めて構える
後転では、構える姿勢が重要です。耳の横に手を添えて、体を丸めるのがコツです。手の平は上に向けてしっかりと開き、耳の横に添えてしゃがみます。そして、体を丸めるために、あごを引いて、おへそを見るようにしましょう。

体を丸めて回転する
勢いを保つためには、体を丸めた姿勢のまま回転することが大切です。構えができたら、その姿勢を保った状態で、勢いよく後方に倒れましょう。お尻が床についた後は、腰、背中、肩、頭を順番に床につけながら回転します。体が伸びてしまう場合は、「最後までおへそを見るように促す」「ボールを思い浮かべ体を丸めて転がるようにアドバイスする」といった方法で、感覚をつかめることがあります。
手の平で床を押す
回転したら、指先から手の平を床につけていきます。そして、手の平で床をしっかりと押すことで勢いをつけます。その勢いで腰を持ち上げ、足の裏で着地して立ち上がりましょう。手の平が床につきにくい場合は、肘が外に向いて開いていたり、肘が床についていたりするケースがあります。手の平をしっかりとつけられない場合は、肘の向きや位置を確認してみましょう。
自宅でできる後転の練習方法
後方に転がることに恐怖心がある場合や、動作の感覚をつかめていない場合は、まず「ゆりかご運動」や「エビの姿勢」を習得しましょう。これらの実践を通じて、後転の動きに馴染み、怖さを和らげながら、ステップアップしていきます。慣れてきたら、子どものペースに合わせて斜面での実践、次に平らな場所で補助つきの練習へと移行します。安全のために、大人がサポートできる場所で行いましょう。
ゆりかご運動
ゆりかご運動は、マットや布団の上で行います。体操座りをして、背中を丸くした姿勢で後ろに転がるように倒れて、元の姿勢に戻ります。この運動は、お腹や背中などの体幹の筋力を鍛えたり、後方に転がる感覚を覚えることで怖さを和らげたりするのに有効です。
エビの姿勢
エビの姿勢は、仰向けになった状態から、足を持ち上げて頭の方向へ倒します。そして、つま先を頭より向こう側の床につけた状態がエビの姿勢です。エビの姿勢を実践する際は、次の2点を意識しましょう。
- 視線をおへそに向けて体を丸める
- 腰を高く持ち上げる
慣れてきたら、手の平を頭の横につけて床を押さえると、より後転に近い動きを体感できます。エビの姿勢は、背中の柔らかさを養い、後転する感覚を馴染ませることで、怖さを和らげるのに役立ちます。
斜面で後転をする
ゆりかご運動やエビの姿勢に慣れてきたら、斜面で後転に挑戦します。後転を成功させるには、勢いよく後方に倒れる必要があります。しかし、勢いが足りず、うまく回れないケースが少なくありません。そこで、斜面を利用することで、勢いをつけて回転できます。斜面は、布団やマットを利用すると手軽に準備できます。自宅で行う場合は、布団を3枚〜4枚程度重ねて、緩めの斜面をつくりましょう。そして、高い方の端から低い方向に向けて後転を練習します。
先ほど紹介したコツを意識しながら、繰り返し実践しましょう。着地までできるようになったら、次の「補助つきで後転をする」ステップに移ります。
なお、傾斜が強すぎると、勢いがつきすぎて危険です。安全に取り組むために、緩めの斜面で実施し、危険なときは大人がすぐに対処できる距離で実践してください。
補助つきで後転をする
斜面で後転ができるようになったら、平らなマットの上で、大人の補助つきで反復するとよいでしょう。大人は、子どもの横について、腰を支えながら回転と着地をサポートします。具体的には、まず大人は膝立ちをし、子どもが回転したときに頭がつく辺りで準備しましょう。そして、子どもが後方に回ったら、両手で左右の腰を持ち上げ、回転と着地を手助けします。
徐々に手助けを減らし、補助がなくてもできるようになるまで繰り返しましょう。
後転に関するよくある質問
Q1.子どもが後転を怖がってうまくできません。どうすればいいですか?
A. 後転は日常生活にない動きで、見えない方向へ回転するため、恐怖心を感じやすい運動です。まずは「ゆりかご運動」や「エビの姿勢」など、後ろに転がる感覚に慣れる練習から始めると効果的です。徐々に恐怖心を和らげ、自信を持って後転に取り組めるようになります。Q2.後転がうまくできない原因にはどんなものがありますか?
A. 主な原因は次の3つです:Q3.自宅で子どもに後転を教える方法はありますか?
A. はい、家庭でも安全にできる練習法があります。まずは「ゆりかご運動」や「エビの姿勢」で後転の基礎感覚を養いましょう。その後、布団を使って緩やかな斜面を作り、回転の感覚を練習します。慣れてきたら、大人の補助つきで平らな場所でも練習できるようになります。まとめ
後転は普段の生活ではほとんど経験しない動きが必要とされ、さらに見えない方向に回ることから不安をもつ子どもも少なくありません。しかし、構えや回転の姿勢を理解し、ゆりかご運動やエビの姿勢を取り入れると、動きに馴染み、不安も軽減します。そして、慣れてきたら、子どものペースに合わせて斜面での実践、次に平らな場所で補助つきの実践へと移行します。安全面に配慮し、危険なときには大人がすぐに対処できる距離で実践しましょう。
ジムオルソでは、お子様の年齢やレベル、やる気に合わせた、少人数制でアットホームな雰囲気のクラスを用意しています。 たとえば、2歳〜3歳が対象の「プレキッズ」をはじめ、小学3年生〜大人が対象の「バク転教室」までさまざまなクラスがあります。体操教室への入会を検討されている方は、ぜひジムオルソの無料体験にお越しください。