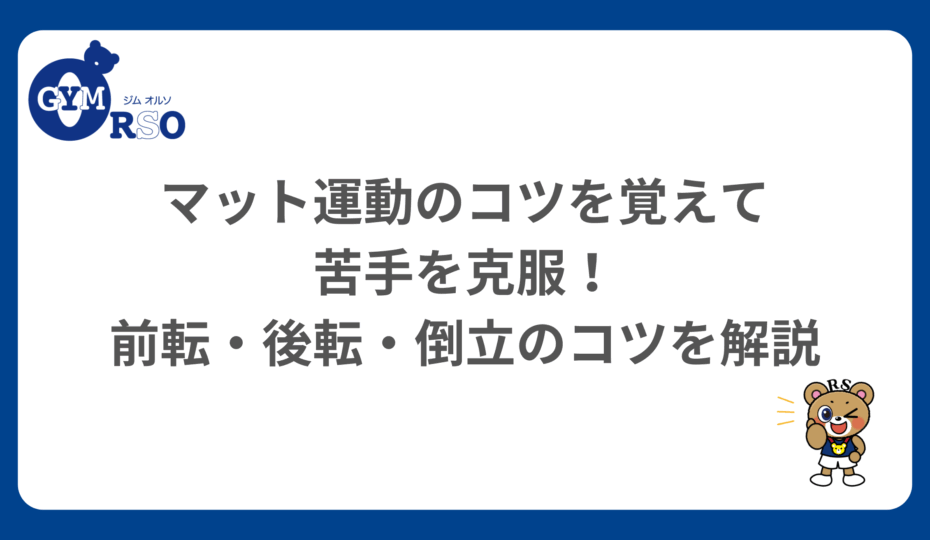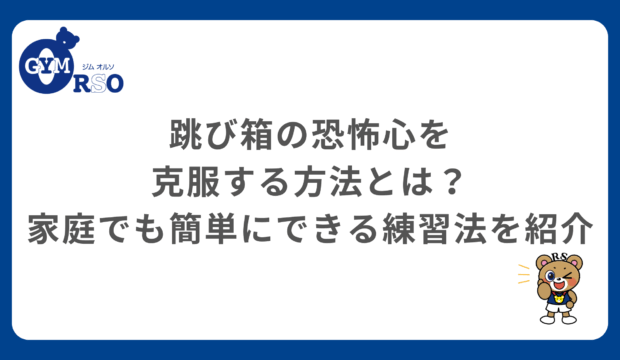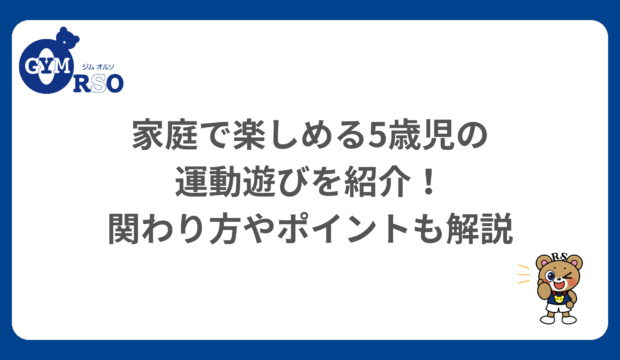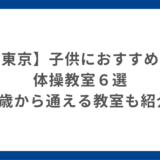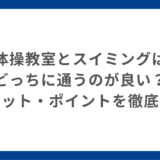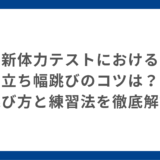しかし、マット運動はコツを掴めば、誰でも簡単にできるようになるのです。
本記事では、マット運動(前転・後転・倒立)の手順と具体的なコツを紹介します。コツを学び、マット運動の苦手を克服しましょう。
マット運動とは
マット運動は、小中学校の体育で行われる運動の一種です。技の種類は、前方回転系・後方回転系・倒立系・宙返り系の大きく4つに分けられます。
学校の授業では通常、宙返り系以外の技を学習します。
もし宙返り系の技をしたい場合は、体操教室に通うことがおすすめです。
体操教室ジムオルソでは、通常基礎を押さえた上でないと取り組めないバク転がコースに限らず挑戦できます。
宙返り系の中でも、特にバク転に挑戦してみたいという人は、ぜひジムオルソにお問い合わせしてみてください。
マット運動の苦手意識を克服する方法
マット運動は普段の生活でしない動きのため、体の動かし方がわからず、苦手意識を持っている人も多いとされています。回転や逆さになることで怖い、けがをしたくないという恐怖心があるのも苦手意識を持ってしまう理由の1つです。
しかし、マット運動はコツを掴めば、けがをせず誰でも簡単にできるようになるのです。
マット運動は、バランス感覚や体幹を養うことにも役立ちます。
得られるメリットも大きいため、苦手を克服してしまいましょう。
ここでは、マット運動に対する苦手意識を克服する3つの方法を紹介します。
柔軟性を身につける
柔軟性を身につけるとスムーズにマット運動ができるため、事前にきちんと準備体操をしましょう。学校の授業では必ず事前に準備体操をしますが、自宅で練習する際にも同様に準備体操をしてください。
日頃のストレッチで体を柔らかくしておくのも効果的です。
コツを掴んで恐怖心をなくす
マット運動はコツを掴めば誰でもできるようになるため、技のコツを理解することが大切です。正しい姿勢や動きを覚えて、適切な方法で練習を重ねてください。
成功体験を得ることで、恐怖心が徐々に弱くなっていきます。
「ゆりかご」で回転の感覚に慣れる
「ゆりかご」は体操座りで両膝をかかえ、あごを引き背中を丸めた状態で前後に揺れる技のことです。マット運動で回転する感覚を掴むのに効果的な練習法です。 恐怖心が強い場合は、まずゆりかごをして、回転の感覚に慣れましょう。
あごを引いておへそを見ながら揺れると背中が丸まって、上手にできます。

前転・後転・倒立のコツ
学校の授業で主流になるのは「前転・後転・倒立」の3つの技です。ここでは、3つの技の手順とできるようになるためのコツを紹介します。
前転のコツ3選
前転の動きの流れは、以下の1~5の順番の通りです。- 進行方向に対して前向きでマットの上でしゃがみます
- 体の前で、肩幅より広めに手をつきます
- お尻を高く上げて、頭をマットにつけます
- 両足でマットを蹴って、後頭部→背中の順でつきながら回転します
- 1回転後、両足を地面について立ち上がります
まずは前転をできるようにしてから、後転・倒立へ進みましょう。
つま先より少し前に手をつく
前転をするときは、つま先からこぶし1つ分ほど前に、手のひらをつけるようにしましょう。手をつく位置が離れていると、上手く回れません。
後頭部をマットにつける
回転するときは、頭の後ろ(後頭部)をマットにつける意識を持つと、きれいに回転しやすくなります。おでこや頭頂部をマットにつけてしまうと、体が左右にぶれてしまったり、頭をつけた部分が痛くなったりすることがあります。
頭をマットにつけるときは、おへそを見るようにすると自然と後頭部がマットにつきやすくなるのでおすすめです。
お腹と太ももを離さないように起き上がる
起き上がるときは、お腹と太ももを離さないように意識しましょう。お腹と太ももをくっつけたまま起き上がることで、勢いを保ったままスムーズに両足で着地できます。
後転のコツ3選
後転の動きの流れは、以下の1~5の順番の通りです。- 進行方向に対して後ろ向きでマットの上でしゃがみます
- 手のひらを上にして耳の横にかまえます
- 背中から後ろに倒れて、マットに手をつき強く押します
- お尻と両足を上げて後方に回転します
- 1回転後、両足を地面について立ち上がります
後転は姿勢も重要なため、補助の人をつけて正しい姿勢ができているかを確認しながら練習してみてください。
後ろに転がる感覚を身につけるために、下り坂になっているところで練習するのもおすすめです。
自分がボールになったイメージで、後ろに転がってみましょう。
お尻はかかとから少し離れた位置におろす
後転をするときは、お尻をかかとから少し離れた位置におろしてください。少し離れた位置におろすことで、回転の勢いをつけられます。
手がマットについたら押す意識を持つ
手のひらがマットについたら、スタンプを押すようにしっかりと床を押してください。前転は足で蹴って勢いをつけますが、後転は手で押す力で勢いをつけます。 そのため、手で床を十分に押せていないと、お尻を持ち上げられません。
このときにお尻が上にあるようにするために、背中を丸めることを意識してください。
足は上ではなく後方に伸ばす
手で床を押したときに、足は上ではなく、後方に向かって伸ばしましょう。後転が上手くできないケースのほとんどは、足を上に伸ばしてしまっているのが原因です。
後方に向かって足を伸ばすと同時に床を手で押すことで、肘がきれいに伸びてスムーズに回れます。
倒立のコツ3選
倒立の動きの流れは、以下の1~5の順番の通りです。- マットの上で足を前後に開いて立ちます
- 両腕を上げ、振り下げながら両手をマットにつきます
- 同時に足を蹴り上げて、足をマットから離します
- 両足を揃えた状態で、身体が床と垂直になるようにします
- その状態で数秒キープして、足をゆっくりとおろします

倒立は、今回紹介した3つの技の中でも1番けがのリスクがあるため、できるようになるまでは必ず補助付きで練習してください。
補助の人がいることで、恐怖心が少なくなって成功の可能性も上がります。
また、倒立には全身の筋力が必要になるため、コツを実践してもできない場合は、全身の筋力を鍛えて、筋力バランスを整える必要があるかもしれません。
床を蹴り上げるときに足を広げない
足で床を蹴り上げるときに、足が広がっているとバランスが崩れてしまいます。勢いも大切なため、強く床を蹴り上げてください。
足を上で揃えるタイミングは焦る必要はありません。
まずは片足でしっかりと蹴り上げて、体をまっすぐ引き上げます。
軸が整った段階で、もう一方の足を揃えましょう。
足を揃えるタイミングをずらすことで、体にかかる負荷が分散されてバランスを整えやすくなるのです。
肘をピンと伸ばす
倒立は全身を両腕で支える必要があるため、肘が曲がっていると上手く力が入りません。全身を支えきれず頭から床に落ちる危険があるため注意してください。
肘をピンと伸ばし、手のひらで床を掴む意識を持つと、バランスが調整できます。
マット運動に関するよくある質問
Q1.マット運動が苦手な原因と克服方法は?
A. 苦手意識の原因は、回転や逆さになることへの恐怖心や体の動かし方が分からないことです。柔軟性を高めるストレッチ、動きのコツを学ぶ、そして「ゆりかご」で回転感覚に慣れる練習が克服に有効です。
Q2.前転・後転・倒立を上達させるコツは?
A. 前転は手の位置・後頭部で回る意識・お腹と太ももを密着させること、後転は手でしっかり押す・背中を丸める・足を後方に伸ばすこと、
倒立は強い蹴り上げ・肘を伸ばす・目線を手の少し前に置くことがポイントです。
Q3.安全にマット運動を練習するために注意することは?
A. 必ず準備体操をして体を温め、恐怖心が強い場合は補助者をつけて練習します。無理のない段階的な練習で、少しずつ慣れていくことが安全に上達する近道です。
まとめ
マット運動は、正しい手順や姿勢を身につけることで、誰でも上達できます。前転・後転・倒立にはそれぞれコツがありますが、恐怖心を和らげたり、柔軟性を高めたりすることで、苦手意識を克服しやすくなります。
「ゆりかご」で回転の感覚に慣れたり、補助をつけて練習したりと、安全に取り組む工夫も効果的です。
少しずつできることを増やしながら、自信をもってマット運動にチャレンジしてみてください。
ジムオルソでは、お子様の年齢やレベル、やる気に合わせた、少人数制でアットホームな雰囲気のクラスを用意しています。
たとえば、2歳〜3歳が対象の「プレキッズ」をはじめ、小学3年生〜大人が対象の「バク転教室」までさまざまなクラスがあります。体操教室への入会を検討されている方は、ぜひジムオルソの無料体験にお越しください。