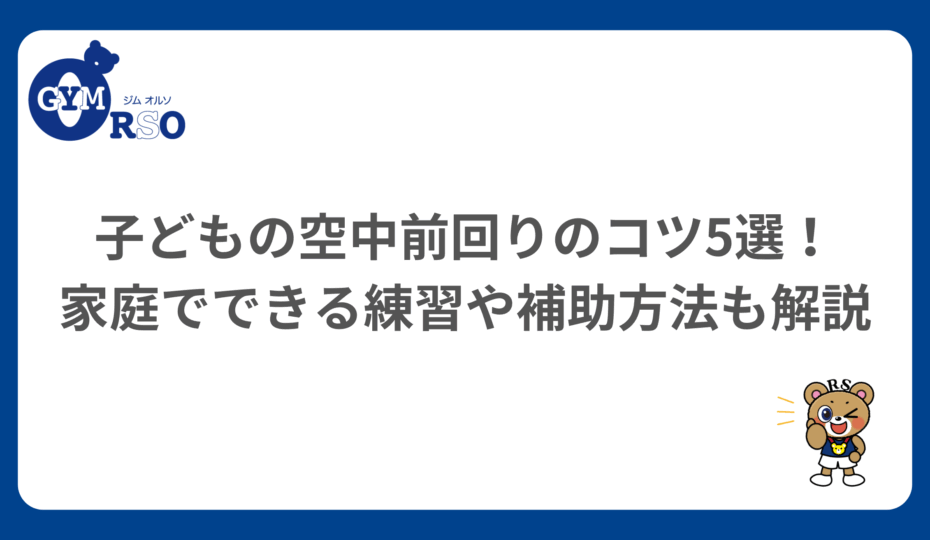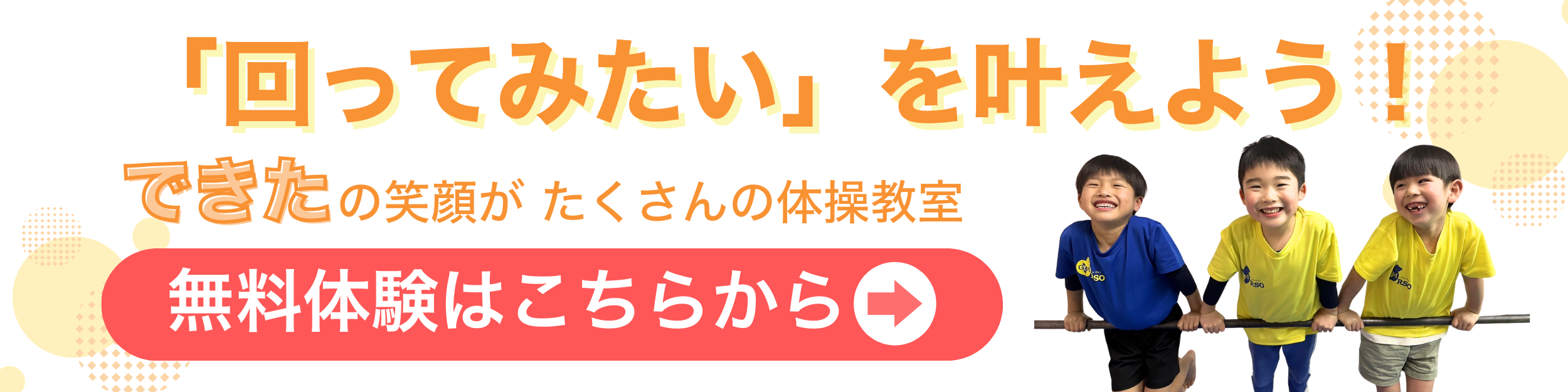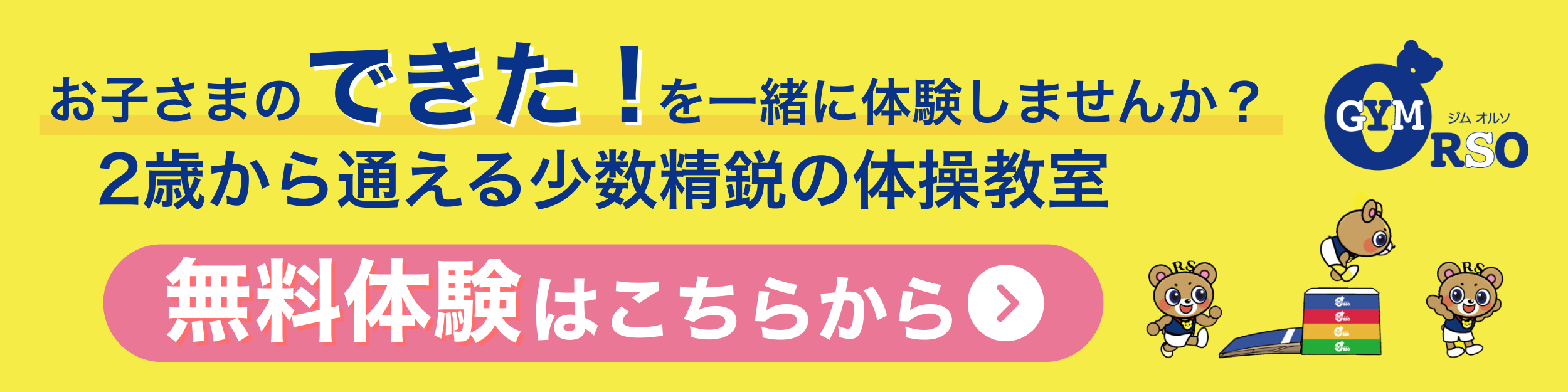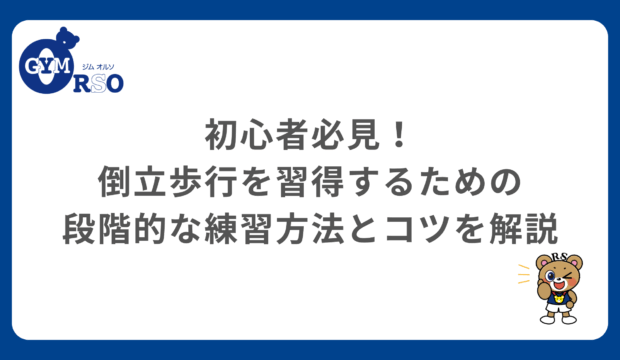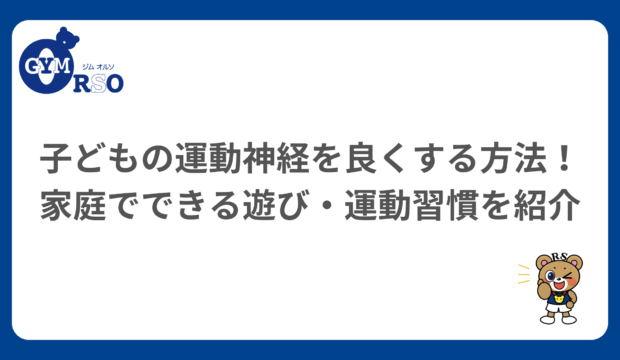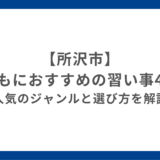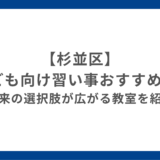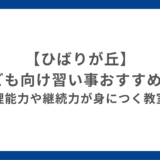難易度が高い技といわれており、空中前回りを苦手とする子どもも少なくありません。
本記事では、空中前回りのコツ5選に加え、補助方法や、家庭でできる練習法、安全に練習するためのポイントを解説します。
空中前回りとは
空中前回りとは、正式には「前方支持回転」と呼ばれる鉄棒技の1つです。鉄棒に乗って腕で体を支える「ツバメの姿勢」から、前方に1回転して再び元の姿勢に戻ります。
逆上がりや空中逆上がりよりも難易度が高いとされており、空中前回りを苦手とする子どもも少なくありません。

空中前回りのコツ5選
空中前回りを成功させるためのコツは、勢いよく回転し、お腹を鉄棒から離さないことです。ここでは、そのための具体的なコツを5つ紹介します。
ツバメの姿勢をとり前を見て肘と背筋を伸ばす
まずは、以下の手順でツバメの姿勢を正しくとります。- 鉄棒を握る(親指は下から鉄棒を握り、残りの指は上から鉄棒を握る)
- ジャンプして鉄棒がお腹にくるように飛び乗る
- 腕とお腹(足の付け根あたり)で体を支える
肘を曲げたり、視線が下へ向き猫背になったりしていると、勢いがつかないため、1回転して元の姿勢に戻れず途中で止まってしまいます。
手の平と太ももで鉄棒を挟む
空中前回りを成功させるためには、お腹と鉄棒を離さないようにすることが重要です。そのために、ツバメの姿勢をとったら、手で鉄棒を下に押しながら、膝を後ろに曲げて太ももで鉄棒を持ち上げるようなイメージで鉄棒を挟み込みます。
これによって、回転中もお腹が鉄棒から離れにくくなります。
なお、膝を伸ばした状態で回転する方法もありますが、より難易度が上がるため、膝を曲げて練習する方が成功しやすいでしょう。
大きく回転する
空中前回りは勢いよく回転する必要があります。そのためには、大きく回転するよう意識することが大切です。
頭を真下に下げるように小さく回転すると、腕や背中が丸まり、十分な勢いがつきません。
勢いが足りないと、頭が下になった状態で止まったり、足が床についたりしてしまいます。
ツバメの姿勢をとり、前を向き、肘と背中を伸ばしたままの状態で大きく回りましょう。
頭が真下になる手前であごを引いて体を丸める
回転の途中で頭が下にきた状態から上半身を起こすときは、体と鉄棒が離れやすくなります。あごを軽く引き、肘は曲げて体を丸め、腕で鉄棒をお腹に引きつけるようにしましょう。
背中が伸びた状態では、鉄棒とお腹が離れてしまい、上半身を起こせず足が床についてしまいます。
手首を前に回す
最後に、体を起こすときのコツです。体を丸めた後、上半身を起こすときは、お腹に力を入れて体を持ち上げ、手首を前方に回しましょう。
そして、鉄棒を押しながら肘を伸ばし、体を持ち上げて元の姿勢に戻ります。
手首を回さないと元の姿勢に戻れないため、足が床についてしまいます。
ただし、回転を始めてすぐに手首を回すと、力が入らなかったり、手が離れて落下につながったりするため、上半身を起こすタイミングで手首を回すことが大切です。
空中前回りの補助方法
補助は、上半身を前方に倒す動きと、起こす動きに対して行います。子どもは、ツバメの姿勢をとります。
大人は子どもと鉄棒を挟んで逆側に立ち、子どもの横から補助しましょう。子ども側の手で背中を押さえ、後ろから前方へ押して、上半身を勢いよく前に倒す動きをサポートします。
頭が下にくるタイミングで、もう一方の手で太ももの裏を支えて鉄棒から離れないようにし、背中を支えて上半身を起こす動きをサポートしましょう。
一連の補助が難しい場合や、子どもが慣れてきた場合は、上半身を起こす動きだけを補助し、上達に合わせて徐々に補助を減らしていきます。
補助に不安がある場合は、体操教室を活用するのもおすすめです。
専門の指導者による適切なサポートを受けながら、正しい動きを習得できます。ジムオルソでは「キッズ②」や「ジュニア」のクラスで、空中前回りに取り組んでいます。

家庭でできる空中前回りが上達する練習方法
ここでは、空中前回りの上達に役立つ家庭でできる練習方法を紹介します。ゆりかご運動と前転は、鉄棒を使わずマットや布団の上で取り組める練習です。
だるま運動
だるま運動は、マットまたは布団の上で行う練習です。体操座りをして背中も丸め、そのまま後ろに転がるように倒れて、再び元の姿勢に戻ります。
だるま運動は、お腹や背中といった体幹の筋力を鍛えるのに有効です。
マット上で前転
前転を練習することで、体を丸める姿勢やバランス感覚を身につけ、さらに空中前回りへの恐怖感を和らげる効果も期待できます。前転はマットまたは布団の上で行いましょう。
まず、しゃがんで手を肩幅に開いて床につきます。
お尻を持ち上げ、肘を曲げながらあごを引いて、後頭部を床につけましょう。
そして肩・背中・腰の順番で床につくように回転し、最後は両足で着地して立ち上がります。
鉄棒でツバメの姿勢
鉄棒でツバメの姿勢をとる練習は、空中前回りで上半身を起こして元の姿勢に戻る動きに役立ちます。以下の手順で練習します。
- 鉄棒を握る(親指は下から鉄棒を握り、残りの指は上から鉄棒を握る)
- ジャンプして鉄棒がお腹にくるように飛び乗る
- 腕とお腹(足の付け根あたり)で体を支える
慣れてきたら、足の位置を変えて行います。
難易度が上がり、空中前回りにより近い姿勢で練習できます。
鉄棒を握った後、足を鉄棒より前(向こう側)の地面につけましょう。
その位置から、膝を曲げて勢いをつけジャンプして、ツバメの姿勢をとります。
足の位置を少しずつ前にずらして練習していきましょう。
鉄棒でぶら下がり
鉄棒でのぶら下がり練習は、次の手順で行います。- ツバメの姿勢をとる
- 上半身を前方に倒し、頭を下にした状態で背筋を伸ばす
- 手を離して太ももで支え、体を前後にぶらぶらと揺らす
- 再度鉄棒を握り、上半身を起こしてツバメの姿勢に戻る
体を丸めるタイミングが早すぎると、うまく1回転できません。
このぶら下がりの練習は、体を丸める前の背筋を伸ばした姿勢や、上半身を起こす動きに慣れる効果があります。
空中前回りができたら、空中逆上がりを成功させるコツも紹介していますので、ぜひチャレンジしてみてください。

2025.05.26
空中逆上がりがうまくいかない原因は?成功させるためのコツも紹介
空中逆上がりは、鉄棒の中でも特に難易度が高い技のひとつです。何度挑戦しても途中で止まってしまったり、体が思うように回らなかったりと、苦戦する子どもも多いでしょう。 しかし、できない原因を正しく理解し、少しずつ克服していけば、誰でも成功に近づけます。 本記事では、空中逆上がりがうまくい...
安全に練習するためのポイント
空中前回りを安全に練習するためには、安全に配慮し環境を整えることが大切です。落下しそうになったときに、大人がすぐ対処できるよう、必ず見守りや補助のもとで練習しましょう。
床にマットを敷いておくことも有効な安全対策です。
また、服装にも注意が必要です。
服の裾がズボンから出ていたり、サイズが大きすぎたりすると、鉄棒に絡まるおそれがあります。
練習するときは、体に合ったサイズの服を選び、裾はズボンに入れておきましょう。
安全への配慮は、ケガを防ぐだけでなく、子どもの恐怖感を軽減する効果もあります。
空中前回りは難易度の高い技のため、習得には時間がかかる場合もありますが、焦らず少しずつ取り組むことが大切です。
安全を第一に考え、できたことを一緒に喜びながら練習していきましょう。
空中前回りに関するよくある質問
Q1.空中前回りを子どもがうまくできないのはなぜですか?
A. 空中前回りは逆上がりよりも難易度が高く、勢い不足やお腹が鉄棒から離れることが失敗の原因になりやすいです。ツバメの姿勢で肘と背筋を伸ばし、お腹を鉄棒に近づけたまま大きく回転することが成功のポイントです。
Q2.家庭でできる空中前回りの練習方法はありますか?
A. マットや布団でできる「ゆりかご運動」や「前転」、鉄棒での「ツバメの姿勢」や「ぶら下がり練習」などが効果的です。これらは体幹を鍛え、回転に必要な感覚を養うのに役立ちます。
Q3.子どもに空中前回りを練習させる時の注意点は?
A. 必ず大人が近くで見守り、補助を行いましょう。床にはマットを敷き、服装は鉄棒に引っかからないサイズを選ぶことが大切です。
安全を第一に、少しずつ練習を進めていくことで恐怖心を和らげ、ケガを防げます。
まとめ
空中前回りは、鉄棒に乗って腕で体を支える「ツバメの姿勢」から、前方に1回転して再び元の姿勢に戻る技です。逆上がりや空中逆上がりよりも難易度が高いとされ、空中前回りを苦手とする子どもも少なくありません。
成功させるためのコツは、勢いよく回転し、お腹を鉄棒から離さないことです。
補助は、上半身を前方に倒す動きと、起こす動きに対してタイミングよく行うことが重要です。
また、安全に配慮された環境を整えることも欠かせません。
適切なサポートを受けながら、安心して取り組みたい場合は、体操教室を利用するのがおすすめです。
ジムオルソでは、お子様の年齢やレベル、やる気に合わせた、少人数制でアットホームな雰囲気のクラスを用意しています。
たとえば、2歳〜3歳が対象の「プレキッズ」をはじめ、小学3年生〜大人が対象の「バク転教室」までさまざまなクラスがあります。
体操教室への入会を検討されている方は、ぜひジムオルソの無料体験にお越しください。